⽇本の軽⾃動⾞市場に迫る⿊船︓中国・台湾勢のEVは新たな脅威となるか︖(2)
- ビッグサイトのモビリティショーは、中国BYDや鴻海のシャープによる軽EV市場参入の前哨戦と聞きました。中国や台湾のEVは⽇本で通⽤するのでしょうか︖
-
先週に続き、ビッグサイトのモビリティショーについて解説します。
「Japan Mobility Show 2025(旧・東京モーターショー)」は、10月30⽇(木)から11月9⽇(⽇)まで東京ビッグサイトで開催されました。そこに出展した中国のBYD、そして台湾の鴻海(Foxconn)傘下にあるシャープという新規参入勢⼒の軽EVが⽇本市場で通⽤する可能性を探るべく、筆者も10月31⽇(⾦)に会場に駆けつけました。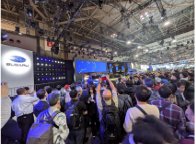
今回、軽EV市場への参入を表明した中国のBYDと台湾・鴻海傘下のシャープは、そのアプローチが全く異なります。両社の戦略を⽐較分析することで、⽇本市場に与える影響の大きさを多角的に⾒ていきます。
■ BYDは戦略転換し軽EV投入を市場に投入
BYD の最大の強みは、バッテリーから⾞両本体までを⼀貫して内製する「垂直統合モデル」にあります。これにより、他社を圧倒するコスト競争⼒を実現しています。さらに、安全性が高く発火しにくい独自開発のリン酸鉄リチウムイオン電池「ブレードバッテリー」の採⽤は、技術的な優位性も担保しています。
これまで高級⾞路線でブランドイメージ構築を図ってきた BYD ですが、2024 年の⽇本での販売台数は2,223台に留まりました。この実績は、高価BYD RACCO(ラッコ)格帯のみでは⽇本市場の攻略が困難であることを⽰唆しています。今回の軽EV投入は、この状況を打開するための、データに基づいた合理的な戦略転換です。
BYD RACCO(ラッコ) 発表された「RACCO」は、⽇本の消費者のニーズを徹底的に研究したモデルだといわれています。人気のスーパーハイトワゴン形式を採⽤し、両側スライドドアを備えるなど、⽇本の軽自動⾞市場の「中⼼部」に狙いを定めているようです。この着想は、2023 年のモビリティショーに来⽇した王伝福 CEO が、⽇本の軽自動⾞市場の独自性に強い関⼼を持ったことがきっかけとされています。⾞名の「ラッコ」は、絶滅危惧種である動物のラッコに由来し、「地球の温度を 1℃下げる」というBYD の企業ミッションを象徴しています。これは、BYD が⽇本の主要セグメントに真正面から挑むという明確な意思表⽰だと指摘されています。

シャープ LDK+ ■ライフスタイルの変革を狙う「シャープ LDK+」
⼀方、シャープの EV 戦略は、従来の自動⾞メーカーとは⼀線を画します。親会社である鴻海(Foxconn)の EV プラットフォーム「Model A」をベースとしつつも、EVを「くらしを豊かにする家電のひとつ」と位置付けています。
このコンセプトを具現化したのが「LDK+」です。「⾞は保有時間の95%が停止している」という事実に着目し、移動しない時間の価値を最大化する「もう⼀つの部屋」というコンセプトを提案しています。運転席が 180 度回転して後部座席と対面できるリビング空間、プロジェクターとロールスクリーンによるシアタールームなど、その発想は自動⾞の枠を超えています。
シャープのアプローチは、⾛⾏性能で競争するのではなく、同社が得意とするAIoT(AIとIoTの融合)技術による家電連携や、V2H(Vehicle to Home)による家庭のエネルギーマネジメントといった、独自の付加価値で勝負する全く新しい戦略です。
両社の戦略は好対照です。BYDが仕掛ける挑戦は、伝統的かつ存亡に関わるものです。既存の自動⾞市場のルールに則り、「性能と価格」という絶対的な武器で⽇本の自動⾞メーカーを、製造効率とコストという「モノづくり」の⼟俵で真っ向からチャレンジする形です。
対照的にシャープの挑戦は、非伝統的かつ概念的なものです。「体験と空間価値」という新たな評価軸を持ち込み、「コトづくり」の領域で⾞の定義そのものを問い直し、従来の性能指標を無意味化しかねない「ライフスタイルの変⾰」を狙っていると言います。こうした状況を⾒ると、中国や台湾資本を背景に持つ企業の軽 EV が⽇本市場で成功を収める可能性は極めて高いと思われます。特にBYDが持ち込むであろう圧倒的な価格競争⼒は、国産メーカーにとって深刻な脅威となり、⽇本の軽自動⾞市場の価格体系を根底から揺るがす可能性があります。
これらの新規参入がもたらす変化は、以下の3点に集約されるでしょう。
- 価格競争の激化: 消費者はより手頃な価格で高性能なEVを選択できるようになります。これにより、国内メーカーは価格戦略の抜本的な⾒直しを迫られることは必⾄です。
- 価値の多様化: シャープの参入は、「移動手段」としての⾞から「可動式の生活空間」へと、EVの価値そのものを多様化させます。これにより、消費者の⾞選びの基準も変化していく可能性があります。
- EV普及の加速: 魅⼒的で多様な製品が市場に投入されることで、これまでEVに慎重だった消費者層の関⼼が高まり、⽇本のEVシフトが加速する起爆剤となるとみられています。これは同時に、充電インフラの整備といった課題解決への社会的な圧⼒を高めることにも繋がります。

BYD Yangwang U9はエンジン⾞の記録を破り、電気
自動⾞(EV)として今年9月に世界最高速度記録を
樹⽴した。⽇本の自動⾞産業は、品質や信頼性といった伝統的な強みだけでは生き残れない新しい時代に突入しています。BYDは「モノづくり」の核⼼である製造コストで、シャープは「コトづくり」という価値提案の概念で、それぞれが⽇本のアイデンティティに揺さぶりをかけています。この二方面からの挑戦にどう応えるか、今後の市場動向に注目したいと思います。
以上

