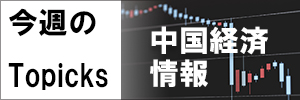-
[
- TOP
- レポート/「中国ビジネス実務指南」
- 第215回 ]
中国ビジネス実務指南― 麗澤大学外国語学部 教授 梶田 幸雄
【第215回】スポーツ用品市場 〜 販売戦略の再構築の必要性
中国で富裕層及び中間所得層が増え、彼らの健康志向が強まり、健康・スポーツ産業に発展チャンスがあると見込まれる。
中国のスポーツ産業は、2012年〜2013年に不調であったと伝えられる。しかし、これが底を打ち、回復基調にある。国家体育総局の2016年末の発表によると、2015年を「スポーツ産業元年」として、2016年の同産業の総生産額は1.7兆元、GDPの0.8%を占めていた。今後は、富裕層及び中間所得層のスポーツに対する関心分野もスキー、低登山、トレッキング、水上スポーツ、フィットネスなど広がりを見せるものと予想される。国家体育総局は、2025年までに中国スポーツ産業の総生産を5兆元にまで高めたいとしている。
こうした中、スポーツ用品企業は、どのような販売戦略を採用すれば良いのだろうか。何をしなくても伸びるという時期でもなくなっている。企業利益を上げるには、それなりの戦略が必要である。
スポーツ用品メーカーの361°(361ディグリーズ)は、2016年に970の店舗を新たに開設したが、一方で1,821の店舗を閉鎖している。これにより、全国の店舗数が7,208から6,357に減少した。「匹克体育」(ピーク・スポーツ)は2016年11月に香港証券取引所の上場廃止となった。現時点で香港証券取引場の上場に踏みとどまっているのは、「安踏」(ANTA)、「李寧」( Li-Ning)、「特歩」(Xtep)、「361°」の4社である。
ただ、361°は低調であったが、李寧は、2016年末時点でフランチャイズ店が4,829店と対前年比4.6%増え、直営店は1,611店と同6.3%増えている。また、安踏は8,489店から8.860店と対前年比4.37%増えた。
それでもeコマース(電子商取引)が増えている中にあって、実体店舗に対する圧力は高まっている。店舗の賃借料、人件費、商品回転コストなどが以前に増してかかるようになっており、価格競争力がなくなってきている。
中国国内企業は、このコスト問題と外国企業との激しい競争の板挟みになっている。外国企業は、中国から生産拠点をより生産コストの安い東南アジアに移し、場合によっては中国国内メーカーよりも価格競争力があるという指摘もある。 ただ、スポーツ用品メーカーとして成功するためには、価格競争力だけではない問題がある。
CITICは、次にように指摘している。“ランニングを例として挙げると、昨今のランニングの聖地である北京奥森体育公園でランニングをする人々の間では、「ランニングシューズがナイキ、アディダスの人はプロのランナーではない。プロのランナーは必ずアシックスを一足持っている」というような会話が行われている。
ここ数年の間、アシックスは「ランニング専門のシューズ」というブランドイメージの確立に成功した。ナイキ、アディダスやニューバランスといった著名スニーカーブランドとの激しい競争を勝ち抜き、販売を急速に伸ばしている。”( CITIC Capital Partners Japan Limited Newsletter Issue No. 7_April 2017) 専門性を強調し、イノベーションを行い、自社製品の差別化を図るという戦略が成功するためには不可欠であるということである。
さらに、中国が今後においてスポーツ産業を育成しようとする場合には、単にスポーツ用品メーカーができるだけでは不足である。このほかにスポーツ施設産業、スポーツ・サービス情報産業がなければならず、スポーツ産業クラスターが形成される必要がある。
このクラスターを形成する健康、医療、観光、アミューズメントもある。また、スポーツ用品には、ファッション産業という位置付けもある。スポーツに関心を持つ富裕層及び中間所得層が、どのような意識でスポーツに取り組もうとしているのかということも重要な問題である。
そうであるから、日本企業が中国のスポーツ産業で市場参入チャンスを掴もうとする場合には、スポーツ用品メーカーとして事業展開するだけでなく、スポーツ施設産業、スポーツ・サービス情報産業といったクラスターを形成することを意識した戦略が適当である。
中国のスポーツ産業は、2012年〜2013年に不調であったと伝えられる。しかし、これが底を打ち、回復基調にある。国家体育総局の2016年末の発表によると、2015年を「スポーツ産業元年」として、2016年の同産業の総生産額は1.7兆元、GDPの0.8%を占めていた。今後は、富裕層及び中間所得層のスポーツに対する関心分野もスキー、低登山、トレッキング、水上スポーツ、フィットネスなど広がりを見せるものと予想される。国家体育総局は、2025年までに中国スポーツ産業の総生産を5兆元にまで高めたいとしている。
こうした中、スポーツ用品企業は、どのような販売戦略を採用すれば良いのだろうか。何をしなくても伸びるという時期でもなくなっている。企業利益を上げるには、それなりの戦略が必要である。
スポーツ用品メーカーの361°(361ディグリーズ)は、2016年に970の店舗を新たに開設したが、一方で1,821の店舗を閉鎖している。これにより、全国の店舗数が7,208から6,357に減少した。「匹克体育」(ピーク・スポーツ)は2016年11月に香港証券取引所の上場廃止となった。現時点で香港証券取引場の上場に踏みとどまっているのは、「安踏」(ANTA)、「李寧」( Li-Ning)、「特歩」(Xtep)、「361°」の4社である。
ただ、361°は低調であったが、李寧は、2016年末時点でフランチャイズ店が4,829店と対前年比4.6%増え、直営店は1,611店と同6.3%増えている。また、安踏は8,489店から8.860店と対前年比4.37%増えた。
それでもeコマース(電子商取引)が増えている中にあって、実体店舗に対する圧力は高まっている。店舗の賃借料、人件費、商品回転コストなどが以前に増してかかるようになっており、価格競争力がなくなってきている。
中国国内企業は、このコスト問題と外国企業との激しい競争の板挟みになっている。外国企業は、中国から生産拠点をより生産コストの安い東南アジアに移し、場合によっては中国国内メーカーよりも価格競争力があるという指摘もある。 ただ、スポーツ用品メーカーとして成功するためには、価格競争力だけではない問題がある。
CITICは、次にように指摘している。“ランニングを例として挙げると、昨今のランニングの聖地である北京奥森体育公園でランニングをする人々の間では、「ランニングシューズがナイキ、アディダスの人はプロのランナーではない。プロのランナーは必ずアシックスを一足持っている」というような会話が行われている。
ここ数年の間、アシックスは「ランニング専門のシューズ」というブランドイメージの確立に成功した。ナイキ、アディダスやニューバランスといった著名スニーカーブランドとの激しい競争を勝ち抜き、販売を急速に伸ばしている。”( CITIC Capital Partners Japan Limited Newsletter Issue No. 7_April 2017) 専門性を強調し、イノベーションを行い、自社製品の差別化を図るという戦略が成功するためには不可欠であるということである。
さらに、中国が今後においてスポーツ産業を育成しようとする場合には、単にスポーツ用品メーカーができるだけでは不足である。このほかにスポーツ施設産業、スポーツ・サービス情報産業がなければならず、スポーツ産業クラスターが形成される必要がある。
このクラスターを形成する健康、医療、観光、アミューズメントもある。また、スポーツ用品には、ファッション産業という位置付けもある。スポーツに関心を持つ富裕層及び中間所得層が、どのような意識でスポーツに取り組もうとしているのかということも重要な問題である。
そうであるから、日本企業が中国のスポーツ産業で市場参入チャンスを掴もうとする場合には、スポーツ用品メーカーとして事業展開するだけでなく、スポーツ施設産業、スポーツ・サービス情報産業といったクラスターを形成することを意識した戦略が適当である。
【 梶田 幸雄氏 プロフィール 】
- ●現職
- 麗澤大学外国語学部 教授
- ほかに中小企業総合事業団国際化支援アドバイザー、富山県貿易・投資アドバイザー、北京航空航天大学法学院兼任教授などを兼務
- ●略歴
- 学歴:中央大学大学院博士後期課程修了。博士(法学)
- 職歴:財団法人日中経済協会、日本能率協会総合研究所、日本経営システム研究所
- ●専門分野
- 中国法、国際企業法、商法
- ●研究業績(主な著書)
- 『チャイナウォール』(通商産業調査会、1993年)、『中国への事業展開と法制度』(国際商事仲裁協会、1995年)、『中国進出企業のトラブル事例と解決法』(日本能率協会マネジメントセンター、1995年)、『中国投資はなぜ失敗するか』(共著、亜紀書房、1996年)、『日中対訳 中国進出企業の各種契約モデル書式集』(日本能率協会マネジメントセンター、2003年)、『中国国際商事仲裁の実務』(中央経済社、2004年)など。