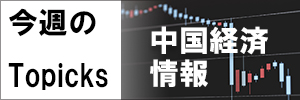-
[
- TOP
- レポート/「中国ビジネス実務指南」
- 第218回 ]
中国ビジネス実務指南― 麗澤大学外国語学部 教授 梶田 幸雄
【第218回】産業ロボット市場の拡大
2017年5月16、17日の両日、浙江省寧波で「第4回中国ロボット・サミット」が開催された。世界各国から専門家、技術者、ビジネスマンら1,500人超が参加した。開幕式の当日だけで、26のプロジェクトが成約され、成約金額は368.74億元の登った。 「中国製造2025戦略」の推進に伴い、産業ロボットのニーズが高まる。
中国ですでに産業ロボット開発のための重点プロジェクトに20億元が充てられている。中国は、2020年までに産業ロボットのクラスターを形成したいとしている。 これには、中国で人口ボーナスがなくなり、人件費が急速に高騰し、生産方式の転換を図らなければならないという要請があるからである。また、高齢化社会になり医療や健康への関心・投資が高まり、災害救済、公共の安全、教育。娯楽産業、重要な科学技術研究分野などにおいてロボットのニーズが高まっているということがある。
そこで、4月6日に工業情報部、発展改革委員会及び財政部は、共同で「ロボット産業発展規画(2016-2020)」を発布した。この規画によると、中国の産業ロボットの現状及び発展計画の概略は以下のようなものである。
2016年の中国の産業ロボット生産台数は、7.24万台で対前年比34.3%の伸びを示した。2015年の全世界の産業ロボット販売台数は24.8万台(対前年比12%増)であったが、このうち中国は6.67万台と世界の販売台数の27%を占めている。2013年以降、世界最大の産業ロボット市場になっている。
現在、産業ロボット育成の重点省は、約20省あり、産業ロボット工業団地が40余ある。ここ2年間に産業ロボットメーカーは400社から800社余へと急速に増え、関連企業はさらに3,400社にものぼる。このうち浙江省だけで280社を数える。
ただ、販売台数は多くなり、メーカーも増えているが、先進国の企業と比べると部品メーカーの技術力が劣るなど周辺産業が弱く、多くの部品は輸入に依存せざるを得ず、高品質の産業ロボットの生産技術で劣っており、企業規模も弱小である。
国家製造強国建設戦略咨詢委員会によると、2020年までに中国の産業ロボットの販売台数は15万台、保有台数は80万台になる。産業ロボットの販売額は約450億元となり、さらにサービス・ロボットを加えると、全ロボット産業の販売額は500億元を突破する。年産1万台以上のメーカーを2〜3社育成し、産業規模は100億元超、国際競争力を備えた産業・企業に育て、全国に5〜8ヵ所の産業ロボット・クラスターを形成する計画である。
今後の重点は、科学技術部高技術中心によると、産業ロボット、特殊ロボット及びサービス・ロボットの3分野である。 今後、産業ロボットメーカー及び関連企業の技術力の向上、とりわけ安全面、性能面や環境面における製品規格の制定といったことが必要になる。そうであると、外国企業との技術提携といったことも必要になると考えられる。
中国政府は、産業ロボット・クラスターを形成したいとし、工業団地の建設が進んでいるが、クラスターを形成し、当該産業をさらに育成しようとするならば、(1)減免税や投融資による財政支援、(2)公平・公正な競争市場の形成も必要になる。外国企業との技術提携を視野に入れるならば、知的財産権の保護もさらに強化する必要がある。
工業情報部、発展改革委員会及び財政部が、これらの問題に関して実施計画を立案することになる。今後、さまざまな問題が出てくるだろうが、中国において当該分野で事業展開をする日本及ぶ外国企業は、中国の関係政府部門に各種の提言を積極的にしていくのがいいだろう。
【 梶田 幸雄氏 プロフィール 】
- ●現職
- 麗澤大学外国語学部 教授
- ほかに中小企業総合事業団国際化支援アドバイザー、富山県貿易・投資アドバイザー、北京航空航天大学法学院兼任教授などを兼務
- ●略歴
- 学歴:中央大学大学院博士後期課程修了。博士(法学)
- 職歴:財団法人日中経済協会、日本能率協会総合研究所、日本経営システム研究所
- ●専門分野
- 中国法、国際企業法、商法
- ●研究業績(主な著書)
- 『チャイナウォール』(通商産業調査会、1993年)、『中国への事業展開と法制度』(国際商事仲裁協会、1995年)、『中国進出企業のトラブル事例と解決法』(日本能率協会マネジメントセンター、1995年)、『中国投資はなぜ失敗するか』(共著、亜紀書房、1996年)、『日中対訳 中国進出企業の各種契約モデル書式集』(日本能率協会マネジメントセンター、2003年)、『中国国際商事仲裁の実務』(中央経済社、2004年)など。